| 子どもの虐待予防事業モデル事例 | ||
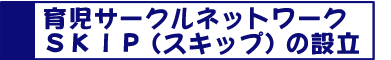 |
||
| 人口:27,272人 高齢化率:18.4% 保健師数:7名 | ||
|
1. 境町の概要 2. 事業の背景 |
3. 事業の内容 4. 事業の成果 |
| 境町は,関東平野のほぼ中央,茨城県の西南部にあり,東京都心部まで約50km,県都水戸市まで約70kmと,全体として首都圏の影響を強く受けている地域です。 面積は46.58km²,関東ローム層に覆われており,ほぼ平坦な地形となっています。町の西南部から東南部にかけて利根川を擁しており,この利根川を利用した水運の河岸及び宿場町として栄え,発展してきた歴史のある町です。 周囲は,岩井市・猿島町・三和町・総和町・五霞町及び千葉県関宿町に隣接しています。 主要な交通手段は自動車で,新4号国道と新利根川大橋及び県道結城・野田線と境大橋が野田市や幸手市など千葉県・埼玉県との連絡口になっています。 平坦な地形を利用して,利根川流域から南北に走る低湿地帯は水田を,大地は田畑を形成しており,温暖な気候から,米,野菜,茶などの栽培が中心となっています。 工業団地の相次ぐ完成により,製造業を中心とした企業が増加し,商業地の変化(路線型の新しい商店の増加)もあり,第2次産業,第3次産業従事者の急増へとつながっています。 また,現在圏央道の整備を踏まえ,工業団地の拡張工事を進めています。 |
||
| 一般的に叫ばれている「育児不安が母親に偏りがち」「地域の中で母子同士が交流する機会が少なく,母子の引きこもりがみられる」「地域力の低下」等,育児を取り巻く傾向が当町でもみられるようになり,地域で子育てを支援していく体制整備の必要性を日々の業務の中から保健師達は感じていました。 平成9年度に第一次母子保健計画を策定する過程で,地域に母親同士で支え合う育児サークルの必要性が明確になり,健康推進課(保健センター)で実施していた母と子の遊びの教室卒業者を募り,平成9年度,平成10年度に2つの育児サークルを健康推進課主導で立ち上げました。育児サークルができたことにより,乳幼児健診や育児相談の際,希望者や必要と思われる対象者に紹介できる受け皿ができ,サークルメンバーも増えていきました。サークルの運営について,最初は保健師による支援が必要でしたが,徐々に自主的に活動できるようになり,その他にもサークルの数が増えていきました。 そこで,育児サークル同士の交流を目的とした交流会を開催しようと考えていたところ,サークルをネットワーク化し,活動の場を広げてみてはどうかという提案があり,その時存在していた町内4つのサークルに声をかけることになりました。そして,平成14年,4つのサークルから代表者が集まり,育児サークルネットワークSKIP(スキップ)が設立されました。 |
||
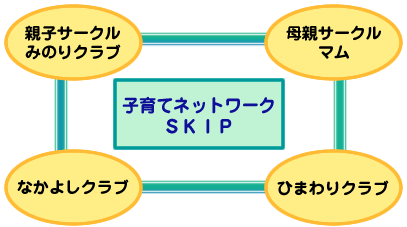 |
||
| 平成14年6月,主に保健センターや伏木文化センターで自主的に活動している4つのサークルが集結し,発足しました。発足に際し,社会福祉・医療事業団(子育て支援基金)助成(事業)という国からの助成金が大きな助けとなりました。 | ||
|
||
| ネットワーク活動の目標は,単に交流に終わるのではなく,育児支援体制を整える必要性を地域に訴えていき,自分たちに出来ることから地域の子育てを支援するということです。自分たちの活動のPRと,引きこもりがちな親子を引っ張り出して,お互いに支え合う良さを分かってもらいたいという気持ちから,様々なイベントを開催しています。 | ||
|
||
|
||
|
||
| 第1回は皆で遊びを通して交流できる内容のイベント,第2回は人形劇,第3回は講演会と初年度に3回ものイベントを開催するに至りました。内容は,皆母親達が話し合いの中から考えたものです。保健師は必要時に助言をする程度でした。平成15年度も2回のイベントを開催しています。 平成15年4月に町立保育園に子育て支援室が開設されることを機会に,サークル活動の場の提供を依頼,また,教育委員会管轄の育児支援関連補助金の支給を受けるなど,行政間での連携を図り,より活動の場が広がっています。 |
||
|
||
| イベントの際には他のボランティア団体(更生保護女性会,食生活改善推進員)や学生(地元の中学校・高校・保母養成校)等にも協力を要請,チラシやポスターを商店に置いてもらう等地域の協力を得ながらの活動になっており,徐々にSkipの存在が知られるようになってきています。協力を依頼するにあたり,活動の趣旨を説明すると,快く協力してくれる団体が多いようです。また,毎回参加者へのアンケート調査を行い,地域で何が求められているか母親達が自ら知ろうとしています。 今年度のイベントには,他市町村からの参加もあり,他でサークル活動をしている方から同じような活動(ネットワーク化)がしたいという声が聞かれています。 また,母親自身が自主的にいきいきと活動され,親たちの元気を感じます。これからの子育て支援は,親のもっている力を引き出すような施策も必要なのではないかと今回の経験から痛感しています。 |
||
| 調査員:全保協専門委員 長谷川 喜美子 全保協主事 齋藤 さやか ヘルスケア総合研究所 正代 剛一 |
| 平成15年度 Topへ戻る |