| 介護予防活動モデル事例 | ||
 |
||
| 人口:10,313人 高齢化率:31.3% 保健師数:5名 | ||
| 介護予防活動モデル事例 1. 藤沢町の概要 2. 事業の背景 3. 事業の内容 4. 成果と課題 |
「健康日本21地方計画」推進活動モデル事例 1. 事業の背景 2. 事業の内容 3. 成果と課題 |
| 藤沢町は,岩手県の南端に位置し,北に千厩町と川崎村,西に北上川をはさんで花泉町,東に室根村,南東に宮城県東和町と本吉町のそれぞれに接し,両磐広域市町村に属しています。 昭和30年4月,旧藤沢町と黄海村と八沢村と大津保村(津谷川は室根村に合併)の4ヵ町村が合併し,現在に至っています。町の大きさは東西16.0km,南北が14.7kmで,面積は123.15km²で,町土の約60%が南部北上山系に連なる山林です。 産業は,複合経営を中心とする農業が基幹産業ですが,近年では,大規模な基盤整備に加え,誘致企業の進出により,農業と商工業が調和した町づくりを進めています。 |
||
| 藤沢町は,病院,保健センター,介護予防センター,在宅介護支援センター,特別養護老人ホーム,デイサービスセンター,グループホーム,老人保健施設,訪問看護ステーション等を備えた福祉医療センターを設置しており,全国に先駆けて当該施設を中核とした福祉医療サービスの充実を図ってきました。その一方で,介護保険制度が施行されるとともに,益々高齢化が進展し,高齢者の健康づくりが重要になってきています。 このような状況において,現在,町内に自主的な介護予防を目的とした会が数多く発足しています。介護保険施行当時,町にあるNPO法人「ボランティアセンター」において,一地域でミニデイサービスを立ち上げました。しかし,各自に交通手段をお任せしていたため,遠隔地の人が通いづらいという問題が生じました。この点について,ある人が自治会の役員会で問題提起したことがきっかけとなり,この自治会で高齢者による月1回のお茶会を立ち上げることになりました。日中一人で留守番をしている高齢者や,一人暮らしの高齢者が,住み慣れた地域の中で,元気に暮らし続けるための集いや語らいの場として,地域の自治会独自で「お茶っこ飲みの会」を立ち上げ,仲間づくり,生きがいづくりを目指しています。 |
||
| 無理のない範囲で長続きさせるようにと,開催回数は月1回を基本とし,参加者の希望を軸に町の介護予防センター等と連携を図りながら実施している他,自治会員登録制による「まぶる会」を結成し,3人1組の輪番制による見守り支援体制をとっています。 また,保健センターでは,平成14年度,町内10地区の健康センターにおいて,「60 歳からの元気応援教室」を実施し,地域での介護予防事業のきっかけづくりの場としました。転倒予防体操,歯科健康講話,料理実習をメニューとし,各地区の保健推進員,食生活改善推進員,自治会長,老人クラブの関係者にも案内状を出しました。 その後,このような動きがきっかけとなり,町のあちらこちらに色々な形で中高年者によるお茶会などの自主グループが発足し,現在,定例で開催しているグループが17グループとなっています。自治会で立ち上げたグループ,老人クラブが中心となっているグループ,気の合う者同士で集まっているグループ,温泉仲間同士で集まっているグループ等多種多様のグループが発足しており,スタイルは全て住民にお任せしています。内容は,話し語り,入浴,保健師による健康相談や健康講話,ボランティアや人材登録者による踊りや体操,手芸,演劇,町職員による歴史や介護保険についての学習会,料理教室など様々です。 また,自分たちの楽しみから一歩前進して,地域集会所の草取り,身よりのない人の墓掃除,80歳以上の人へのふれあい弁当の提供といったボランティア活動を行っているグループもあります。開催回数は,月1回程度を基本としています。交通手段は各自にお願いし,会員制で運営しており,参加者の多くが,無理のない範囲で楽しみとして参加しています。 行政としては,このような住民の活動を,介護予防センターが開催する地域ケア会議を中心に支援しています。会議には,地域のお茶会グループの代表,役場関係課(自治振興推進室,生涯学習課,介護支援センター,シルバーセンター,保健センター),関係機関(NPO,社会福祉協議会)が参加し,各グループの代表者からはそれぞれのお茶会の様子の紹介と課題,関係課や関係機関からは提供できるサービスメニューの紹介を行っています。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 新たにお茶会を立ち上げようとしている人たちにも見学してもらい,立ち上げのための支援の場にもなっています。実際,各種メニューを利用するにあたっては,介護予防センターが中心となって,講師との交渉や財政的支援を行っています。介護予防センターは保健センター内にあり,保健師が1名配属されています。健康推進係の4名の保健師と連携をとりながら,事業を効果的に支援しています。また,町内には44の自治会があり,町の職員全員による地域分担制がとられていて,役場関係課や関係機関と連携がとりやすい体制ができています。 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | 茶飲み話に花を咲かせ,おしゃべりを楽しみ合いながら,笑い声がたえない明るいおしゃべり活動 | |
| ○ | 利用者の心配事の解決のための話し合い | |
| ○ | 保健師による健康学習,警察官による交通安全・防犯の話,消防署員による防災の話,救急救命の話など | |
| ○ | 手芸,囲碁,将棋,トランプなど室内で出来る活動 | |
| ○ | カラオケ,謡曲,詩吟など声を出す活動 など | |
| ○ | 転倒予防体操,玄米ニギニギ体操 など | |
| ○ | ニチレクボールなどニュースポーツ など | |
| ○ | 昔の子どもの遊び〜思い出してやってみよう | |
| ○ | 昔の料理〜思い出して作ってみよう | |
| ○ | 昔話〜思い出して語り合ってみよう | |
| このように,地域に中高年を中心としたお茶会などの自主グループが数多く出来ていることで,地域のお年寄りの楽しみが増え,安心感が生まれています。また,地域住民の高齢者に対する関心が増しています。健康寿命の延伸には,生活習慣病対策も重要ですが,住民がお互いに支え合いながら生活していくことも重要です。今後も,町では住民主体の活動を側面から支援していきたいと考えています。 課題としては,地区によってお茶会グループがうまく立ち上がるところと,そうではないところがある点です。地区にリーダーとなる人がいれば,スムーズにお茶会グループが立ち上がるのですが,そうでないところはなかなかうまくいきません。今後は,グループがない地区にもお茶会グループが立ち上がるよう,行政としても積極的に支援していきたいと考えています。 |
||
| 「健康日本21地方計画」推進活動モデル事例 | ||
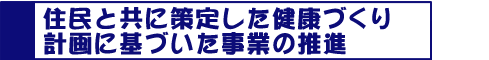 |
||
| 当町においては,健康日本21計画が打ち出される以前から,住民の生活改善を重視した一次予防活動に積極的に取り組んでいます。中でも運動と喫煙に重点を置いた活動に注力しています。運動については,将来のQOLの面から筋力の維持が重要であること,喫煙については,喫煙に関係する疾患の有病率が高いことから取り組んでいるものです。事業の実施にあたっては,住民の主体的な健康づくりへの参加と,好ましい健康習慣が維持されていくための環境整備,健康な地域づくり,ということを意識しています。 また,昨年度から今年度にかけて,住民や関係機関,関係者の参加の下に話し合いや実態調査を重ねながら,町の健康づくり計画を作り上げましたが,その中でも,「食生活」「歯科」「運動」「お酒・たばこ」「心・ゆとり・地域」「子ども」の六つの分野で行動目標と具体的取り組みを示しました。住民がお互いに支え合い,励まし合いながら健康な地域・環境づくりができるように,行政がすることだけではなく,個人・家庭・地域・学校・職場ができることを行動計画としました。特に,運動や喫煙については,仲間づくりや声がけをすることを目標に定めています。 |
||
|
||
|
||
| これら二つの教室を実施するにあたっては,国保ふじさわ町民病院や,スポーツ振興課,シルバーセンターといった関係機関との連携を図りながら進めています。プール職員には,スタッフの一員として教室に参加してもらっています。 また,病院では,外来受診者で肥満,高血圧,高脂血症,糖尿病等の軽い有所見者に対して教室を紹介してもらったり,医師による健康講話をお願いしています。 |
||
|
||
|
||
|
||
| これまで実施してきた各種教室などについて,今後も内容の充実を図りながら継続し,運動習慣や禁煙のきっかけの場を提供していきたいと考えています。また,仲間づくりを積極的に支援し,色々なグループが数多く作られることを目標としています。これに加えて,住民や自治会組織,学校保健会,PTAなどの関係機関と話し合いながら,住民参加の形で事業を推進していく計画です。特に自治会については,健康づくり計画が自治会協議会との協働策定という位置づけになっていることから,保健師自身が各自治会に出向き,地域にあった活動を推進していく予定です。 ちなみに,今年度は,地区健康センター10カ所に出向いて健康講座を実施しました。健康づくり計画の内容を紹介し,寸劇を通して地域みんなで健康づくりがしやすい環境づくりを進める必要性を訴えました(ヘルスプロモーションの考え方の重要性)。さらに,健康づくり計画の周知と普及推進を目的に,行動計画の内容をポスターにして全戸に配布し,健康づくりシンポジウムを開催しています。住民からは,予想以上に反響があり,健康な地域づくりの兆しがみられています。 町としても,健康づくりにおいても住民が主体的になれるように,保健師が今後も支援していきたいと考えています。 |
||
| 調査員:全保協専門委員 有原 一江 ヘルスケア総合研究所 正代 剛一 |
| 平成15年度 Topへ戻る |