| 人口:21,340人 高齢化率:22.3% 保健師数:6名 | ||
| 1. 浪岡町の概要 2. 「健康なみおか21」策定に取り組んだ背景 3. 計画策定にあたっての保健師の位置づけ 4. 情報収集の方法 5. 健康づくりの目標(スローガン) 6. 計画策定のための組織 |
7. 「健康なみおか21」における事業の柱 8. 保健事業の内容 9. 数値目標の設定 10. 「健康なみおか21」策定の成果 11. 今後の課題 |
| 1)自然条件 浪岡町は,青森県のほぼ中央部に位置し,東西約19km,南北約17kmの町域を有し,総面積は約132.13km²となっています。 町の中央部をJR奥羽線,国道7号線,東北縦貫自動車道等が走っており,町の北東部に新青森空港が開港したのに伴い,首都圏へのアクセスが図れるなど高速交通体系の主要な役割を果たしています。 2)産業構造 浪岡町の産業は,りんごと米を基幹作物とした第一次産業(農業)が主要産業で,特にりんごは,全国町村第一位の生産量を誇っています。 平成12年の国勢調査によると,就業人口は11,043人で,総人口の52.9%を占めており,第一次産業は2,759人(25.0%),第二次産業は2,512人(22.7%),第三次産業は5,741人(52.0%),分類不能が31人(0.3%)になっています。 3)人口構成 浪岡町の人口は,近年において昭和55年をピークに概ね減少傾向を示していましたが,平成12年の国勢調査では微増しており,平成14年3月31日現在の総人口は21,340人で,6,668世帯が生活しています。65歳以上は4,766人で,高齢化率は22.3%となっています。 |
||
| 浪岡町は,平成13年2月に「浪岡町長期総合計画」を策定しました。当計画では,「たくましい浪岡町」「やさしい浪岡町」「さわやかな浪岡町」を3本柱の基本理念として位置づけ,諸施策の達成実現を目指しています。また,平成9年度から5か年計画として「浪岡町母子保健計画」を策定し,これを推進してきました。 これまで成人を含めた保健計画がなく,計画を策定したいと思っていたところ,青森県が国の「健康日本21」をふまえて平成13年に「健康あおもり21」を策定し,これをうけて私たちも保健所に計画策定の協力を求めたところ,「一緒に立案しよう」という流れになり,すぐに予算化され,早期に計画立案に着手する運びとなりました。 |
||
| 浪岡町においては,保健師がリーダー,つまり中心的な立場で計画策定を進めることができました。 また,首長や上司は,策定にとても協力的であり,スムーズに計画立案を進めることができました。 |
||
| 地域の実態を知るための調査は特に行いませんでした。そこで,町民や関係機関,町職員で構成された計画策定作業部会において,成人・老人保健,健康づくりについて3回に渡って話し合いを行い,町民をはじめ多くの関係機関の方々から下記のように様々なご意見をいただきました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 部会で出された意見(一部を抜粋して掲載) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 下記の資料を収集・活用し,浪岡町の人口動態,疾病構造の状況,関係機関とマンパワー,各種健診の受診状況等について把握しました。 ○収集・活用した資料 ・青森県保健統計年報 ・国民衛生の動向 ・浪岡町保健活動のまとめ ・市区町村生命表など |
|
| 「浪岡町長期総合計画」でのスローガンを,「健康なみおか21」にも流用しました。 「健康なみおか21」でのスローガン |
|
| 浪岡町保健計画策定委員会及び浪岡町保健計画策定作業部会を立ち上げ,第1回の合同会議を平成13年6月27日に開催しました。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 計5回にわたって浪岡町保健計画策定会議を開催しました。第1回と第5回を合同会議,第2回〜第4回までを作業部会としました。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 事業の柱は,厚生省(現厚生労働省)が掲げた柱をベースとして設定しました。 | |
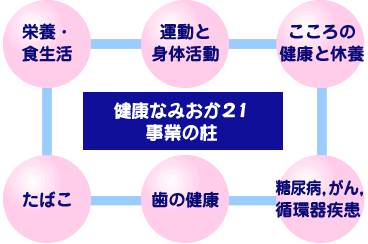 |
|
| 浪岡町が実施した平成13年度基本健康診査の体脂肪測定判定結果では,40歳から64歳の43.3%の男性,59.3%の女性が肥満でした。これは,受診者のおよそ2人に1人が肥満であることを示しています。 肥満は生活習慣病の大きな要因であることから,浪岡町民が「肥満を予防し,楽しく健康的な食事ができる」ことを目指します。 |
||
| (1)さわやか教室 健康に関心がある40歳以上の町民を対象に,調理実習・健康講話・運動などを実施する。 (2)基本健康診査事後指導 基本健診受診者の中で生活習慣改善指導の必要な人を対象に,健康相談・健康教室等を実施する。 (2)減塩教室 食生活改善推進員の協力により,減塩に努めるための調理実習を実施する。献立については,推進員の研修会で検討する。 (4)健康献立の普及 (5)りんごを使った健康づくり―浪岡りんごの普及― (6)食生活改善推進員による健康づくり事業 (7)基本健診(身長,体重,BMIの測定) (8)個別健康教育(高血圧,糖尿病,高脂血症) 基本健診受診者の中で,高血圧・糖尿病・高脂血症の「要指導」と判定された人を対象とし,希望を募る。6ヶ月間の保健師の面接指導等で生活習慣の改善を図り,その間に4回の尿検査または血液検査で改善の評価をする。 (9)小児生活習慣病予防教室 (10)子供を対象とした魚料理の普及 (11)昔の食事の伝達 (12)一人暮らし老人の食事サービス事業 一人暮らしの高齢者を対象に希望を募り,1回250円の会費で昼食と入浴を提供する。食事作りはボランティアが行い,また歌や踊りの披露など多くの人の協力もある。 |
||
| 平成13年度基本健康診査の結果,日常生活の改善が必要とされた方に対して運動に関する意識調査を実施しました。その結果は,自分が運動不足だと思う人は56.8%,思わない人は35.2%でした。また,仕事以外の時間に汗をかくような運動をしている人は13.6%,していない人は64.8%でした。「運動不足だと思っていても運動できない」「仕事で体を動かしているので運動不足とは思わない」など,日常生活の改善が必要とされた方が,運動に対して持つ意識は様々です。生活習慣病の予防や改善のためには,意識的に体を動かし継続することが大切です。そこで,「生活の中に運動を取り入れ,健康の保持・推進を図る」ことを目指します。 | ||
| (1)さわやか教室・運動 (2)健康教室 体を動かすことが,健康づくりにとって必要であることを意識し,運動をテーマとした健康教室 (3)基本健康診査事後指導 (4)ウォーキングマップの作成 浪岡町でウォーキングを楽しめるようにウォーキングコースを紹介した地図を作成する。 (5)雪を楽しめるスポーツの普及 (6)スポーツサークルの啓蒙 (7)町運動施設の効果的活用検討会 (8)健康づくり運動イベントの実施 町民運動会,元旦マラソン,ウォーキング,ハイキング,スポーツフェスティバル,球技大会等 |
||
| 近年,全国的に壮年期の自殺者が増え,新聞などでも大きく取り上げられています。浪岡町においても平成7年から9年までの3年間における自殺による死亡者数が7人であったのに対し,平成10年から12年までの3年間では22人となっており,急激に増加しています。 また,町民からも,「こころの病気を気軽に診てもらえる医療機関や相談場所についての情報が,いつでも誰にでもわかることが大切ではないか」との意見が出されています。こころの健康づくりには,休養を取り入れながら上手にストレスを発散し,ストレスとうまく付き合っていくことが大切な要素となります。これらのことを踏まえ,今後ますます重要な課題となることが予測される「こころの健康づくり」に取り組んでいきます。 |
||
| (1)こころの健康教室 一般町民を対象として,年1回講演会を実施 (2)こころの相談 月1回,精神保健福祉相談員や保健師が個別に相談に応じている(要予約)。 (3)医療機関紹介マップ (4)さわやか教室 (5)B型機能訓練教室 痴呆予防を目標に,地域で月1回の健康教室を,地域の老人クラブや町内会が主体となって行う。 (6)特定疾患交流会「仲間と語る朝(あした)の集い」 パーキンソン氏病や脊髄小脳変性症など治療法が確立していない病気をもつ人や家族の交流会を年7回実施している。 (7)老人福祉センターの利用(高齢者入浴サービスなど) (8)精神障害者家族会「ぼんじゅの会」 精神障害者の家族の親睦を深めるため結成され,事務局は健康福祉課健康推進班となっている。 (9)心配ごと相談 |
||
| 町の喫煙率は,平成13年度基本健康診査受診者(40〜64歳)の生活習慣の状況からみると,男性49.2%,女性3.5%であり,平成7年度国民栄養調査の40歳から69歳までの男性53.2%,女性9.2%と比べて,やや低い状況にあります。しかし,妊娠中の喫煙率は14.4%(平成13年4月〜10月),中学生の喫煙率は4.4%(平成13年調査)となっており,次世代を担う若い人たちへの働きかけが今後益々必要です。 | ||
| (1)個別健康教育(禁煙) 禁煙を希望する町民を対象に3ヶ月間にわたって保健師がサポートする。 (2)禁煙普及啓蒙活動及び禁煙外来の紹介 (3)公共施設の禁煙・分煙の徹底 (4)妊娠届出時の窓口指導・妊娠中の禁煙 (5)両親学級・受動喫煙の学習 (6)禁煙教室(小学4年生,中学1年生) 小学4年生と中学1年生を対象にたばこの害について学習する。授業の一環として行う。 |
||
| 平成8年度に実施した浪岡町の実態調査から,「自分の歯を20本以上有する人」の割合が,40歳から49歳では69.9%,50歳から59歳では40.8%,60歳から69歳では17.5%,70歳以上では12.6%となっています。自分の歯を失うことが,全身の健康に影響を与え,健康状態や生活の質を大きく左右する重要な要因といえます。このことから,「いつまでも,自分の歯で,おいしく食事がとれる」ことを目指します。 | ||
| (1)歯の健康相談 歯科衛生士が訪問,歯科検診の受診者で口腔衛生指導の必要な人,在宅寝たきり者の介護をしている人などに,歯の磨き方や口腔のケアを指導する。 (2)健康教室 (3)歯周病検診 40歳,50歳の女性を対象に,子宮がん,乳がん集団検診の中で実施する。 (4)訪問歯科検診 65歳以上(障害のある人については40歳以上)の在宅寝たきり者に,町内の歯科医が訪問し,歯の検診をする。平成6年度から実施し,在宅歯科診療にも結びつけている。 |
||
| 平成12年の浪岡町の死亡順位は,1位が悪性新生物,2位が脳血管疾患,3位が心疾患と全国と同様の傾向を示しています。その中で,標準化死亡比(年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較するための指標,標準集団の標準化死亡比を100とし,値が大きいほど全体の傾向より死亡者が多いことを示す)をみると,糖尿病(男女とも)及び大腸癌(男)が160前後で,浪岡町の死亡に大きく影響を与えていることが示されました。特に糖尿病は近年増加傾向が著しく,また,循環器疾患による死亡にも深く関係しています。健康な生活をおくるためには,病気の早期発見と共に,生活習慣病の改善が今後の大きな課題となります。 | ||
| (1)健(検)診体制の設備 (2)経年的な健康管理システムの整備 個人の健診結果を経年的に管理するためのコンピューターシステムを開発・整備する。 (3)基本健診事後指導 (4)各種健康教室 健康づくりをテーマに保健福祉センターなどで全町民を対象に実施する健康教室の他,地域の要望に応えて行う教室など,様々な内容で年間90回程度実施している。 (5)疾患別健康相談 (6)個別健康教育(糖尿病,高脂血症,高血圧,禁煙) 6ヶ月の期間に,4回の血液検査や尿検査を行い,栄養・運動・休養の取り方について,個人の生活状況に合わせ定期的に保健指導を受けながら生活改善を行う。 (7)保健協力員の活動強化 保健協力員は,地域の中で健診などの啓蒙を行うほか,自主的に健康教室の開催を行う。 |
||
| 具体的目標値を設定するのは大変難しく,目標を「増やそう」「減らそう」という表現にとどめました。 | |
| 計画の策定により,事業を全体としてみることができるようになりました。これまでは,目標に対する意識が担当者や部門によってばらばらでしたが,皆で検討し,同じ目標に向けて各種事業を進めることができるようになりました。 | |
| ○ | この計画を策定したことにより,保健業務も増え,忙しい状況が続くことに変わりがないと思います。今回,保健師間で業務のあり方が明確になり,しっかりとした目的意識をもつことができたので,今後は,毎年評価をしながら住民と一体となり,この計画を進めていきたいと思います。 | |
| ○ | 「自分の健康は自分でつくろう」という健康づくり運動を展開していくために,これまでの行政主導の事業が,ひとつでも住民主導の事業に転換できればよいと思います。そこに保健師として,できるだけサポートしていきたいと考えています。 | |
| ○ | 健康長寿の延伸を図るために,地域の協力を得ながら予防活動に取り組んでいきたいと思います。 | |
| ○ | 今まで以上に関係機関と連携を図り,スムーズに事業が進められるよう体制づくりをしたいと考えています。 | |
| 調査員:全保協常務理事 山田 喜久夫 ヘルスケア総合研究所 正代 剛一 | ||
| 平成14年度 Topへ戻る |