| 人口:67,852人 高齢化率:16.5% 保健師数:11名 | |
| 1. 「健康はちまん21プラン」策定に取り組んだ背景 2. 計画策定にあたっての保健師の位置づけ 3. 情報収集の方法 4. 健康づくりの目標(スローガン) 5. 計画策定のための組織 6. 「健康はちまん21プラン」における事業の柱 |
7. 保健事業の内容 8. 数値目標の設定 9. 「健康はちまん21プラン」の意義 10. 今後の課題 |
| 近江八幡市では,保健師業務の量が増えてきているとともに,業務の内容も曖昧になってきている状況にありました。保健師としては,一次予防を重視した活動を望んでおりましたが,ここ数年,介護保険等の影響で福祉サイドへの保健師の異動があったり,業務内容の面においても福祉の色合いが濃くなり,業務内容の整理・見直し(保健師業務の内容の明確化)が必要な時期に来ていると感じていました。 そのような折,一次予防を重視した「健康日本21地方計画」がスタートしました。「この機会を,地域住民の意見や要望を聞きながら保健師業務を見直すチャンスとして生かそう」と考え,計画に早期に着手することにしました。また,たまたま成人保健計画の立案に着手していたところでもあり,これを「健康日本21地方計画」に活かして立案しようということになりました。 |
||
| 近江八幡市では,保健師がリーダー,つまり中心的な立場で計画策定を進めることができました。 また,首長や上司は,計画策定にとても協力的であった他,今回の計画立案を通して,関連部署や関係機関との連携を深めることができ,とても楽しく計画立案を進めることができました。 |
||
| 平成12年2月に,20〜64歳までの近江八幡市の住民2,013名(住民基本台帳より無作為抽出)を対象に,健康実態調査を実施しました。 調査項目は,歯科保健,健康に対する意識,健康食品,食事,たばこ,運動,飲酒,睡眠,社会活動に関すること,ストレス,行政に対する要望など多岐に渡り,近江八幡市民の健康状態や,生活習慣,健康活動,健康への意識などについて明らかにすることができました。(住民の思いをきくことができました。) また,併せて各種団体へのニーズ調査を実施しました。 |
||
| 滋賀県から資料の提供を受け,近江八幡市の人口静態・動態,各種健診の受診状況,国保による医療費,疾病構造等の状況を把握・分析しました。 | ||
| 市の総合発展計画でのスローガン | ||
| 「健康はちまん21」でのスローガン | ||
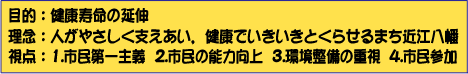 |
||
| 平成11年12月 健康はちまん21プラン策定委員会を立ち上げました。 | ||
|
||
| 地域の実態調査を分析するにあたり,街の状況を細かく点検し,具体的な対応策を立案するために,ワーキング部会を組織しました。 ワーキング部会は,保健センターが事務局を担当し,老人保健事業検討部会,栄養・運動・環境部会,施設・環境部会,自主グループ検討部会の4部会から構成されています。 |
||
|
||
| 各部会のメンバーが街角ウオッチング,訪問による実態調査や福祉体験学習など自主的に企画し,メンバー同士の話し合いを通して各種対策について検討しました。検討内容の報告機会の場として,平成12年9月2日に市民会議を開催しました。 | ||
| 事業の柱は,厚生省(現厚生労働省)が掲げた柱が近江八幡市にも合っていると考え,ほとんど同じ内容で柱を設定しました。 | ||
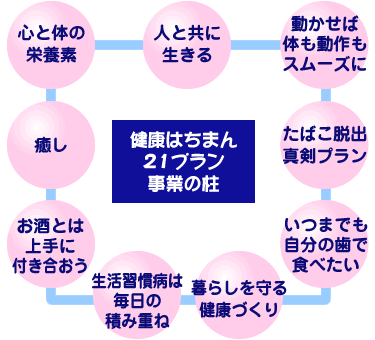 |
||
|
(1)食事の摂取についての正しいあり方の教育・啓発 (2)個人ライフスタイルに応じた食事の情報提供 (3)カロリー表示・ヘルシーメニューの提供ができる市内飲食店の整備 (4)JR駅の市管轄区域に「朝ご飯食べてきた?」の表示 (5)「朝食」や親子クッキング教室の開催 (6)目的・対象別料理教室(中高年男性,旬の食材,郷土料理など)の開催 (7)「朝ご飯を食べるまち」宣言 (8)出前の料理教室 |
||
|
(1)健康プロデューサー(まちづくりの仕掛け人)の育成と派遣 (2)市民自主グループの設立と活動の支援 (3)高齢者・障害者の交流の場づくりと活動の支援 |
||
|
(1)運動の効用についての教育・啓発 (2)運動をする機会・教室(ウォーキング,軽スポーツ等)の定期開催 (3)健康運動指導士の設置 |
||
|
(1)気軽に相談できる窓口の増設 (2)ストレス・心の相談窓口の情報提供 (3)安らぐ方法や場所の紹介 (4)精神保健ボランティアの活用・育成 (5)うつ病の早期発見システムの検討 (6)精神障害者共同作業所や家族会と地域住民との交流 (7)引きこもり,閉じこもり,不登校者の本人・家族を対象とした集まりの場の設定・整備 |
||
|
(1)禁煙に関する健康教育の開催 (2)禁煙に取り組む自主グループの育成 (3)禁煙の啓発・普及 (4)禁煙指導ができる医療機関の情報提供 (5)未成年者に“たばこ”を売らない販売体制の徹底 (6)公共機関における分煙の場の設置 (7)禁煙・分煙推進店の拡大・紹介 (8)「会議等の場では灰皿を出さない」宣言 |
||
|
(1)節度ある適度な飲酒の知識の普及・啓発 (2)未成年者に“お酒”を売らない販売体制の徹底 (3)断酒会・家族会への支援 (4)断酒指導ができる医療機関の情報提供 (5)祭りや自治会行事などで,未成年者に飲酒をすすめない啓発 |
||
|
(1)歯の健康教育の開催 (2)歯科検診の実施 (3)歯科医院のバリアフリー化をはかる (4)障害者の受け入れが可能な歯科医療機関の情報提供 (5)フッ化物の使用の推進 (6)歯によい食品・器具の情報提供 (7)ノージュースデイの取り組み |
||
|
(1)生活習慣病予防の健康教育 (2)生活習慣病予防のための情報提供 (3)医療機関のバリアフリー化 (4)健康づくり関連の自主グループの育成・支援 |
||
|
(1)環境に関する自主グループの育成・支援 (2)エコクッキング教室(野菜の皮を使った料理やガス・電気・水などを節約し,廃油処理も工夫するなど自然環境を考えた料理教室)の開催 (3)企業への環境を守るための教育・啓発 |
||
| 上記のように,以前よりも新規の事業が増えました。これまでの事業の中で,削減・縮小したものは一つもありません。ただ,保健師だけの事業として理解されていたものが,地域の関係機関との連携のもとに事業を進めることが確認され,とてもよかったと考えています。 | ||
| 数値目標を設定しておらず,これからの作業です。ただ,数値目標の設定に際して,数値の妥当性や根拠を明らかにすることが難しく,話し合いを通して妥当と思われる数値を決めていくことになると思います。 | |
| 地域をあげて予防活動に取り組むことの意義を確認することができました。計画策定を通して,住民と行政の距離が大きく縮まったと感じています。 | |
| 保健師の役割,地域の関係機関の役割が明確になるとともに,住民ニーズを直接的に把握することができ,とても意義があることだと感じました。また,ぼやけてきていた保健活動のあり方を再認識することができました。保健活動の原点である地域で暮らす住民の中にこそ,活動の場があることを再認識することができました。 | |
| 住民は,行政に対して多くの要望をもっており,今回の計画策定を通して,自分たちの意見が計画に反映されるということで,「言ってもしょうがない」という意識から「どうにかしてくれる」という意識に変わったと思われます。 | |
| 今回の事業の中で,私たちが目玉と考えているのは「交流」です。 | ||
|
||
| 行政の活動には限界があり,交流を通して様々な市民活動が生まれれば,行政の活動を補うことができます。行政主導の事業が,少しでも住民主導の事業に転換していくよう,私たちもできるだけ住民をサポートしていきたいと考えています。 | ||
| 調査員:滋賀県野洲町 竹澤 良子 ヘルスケア総合研究所 正代 剛一 | ||
| 平成13年度 Topへ戻る |